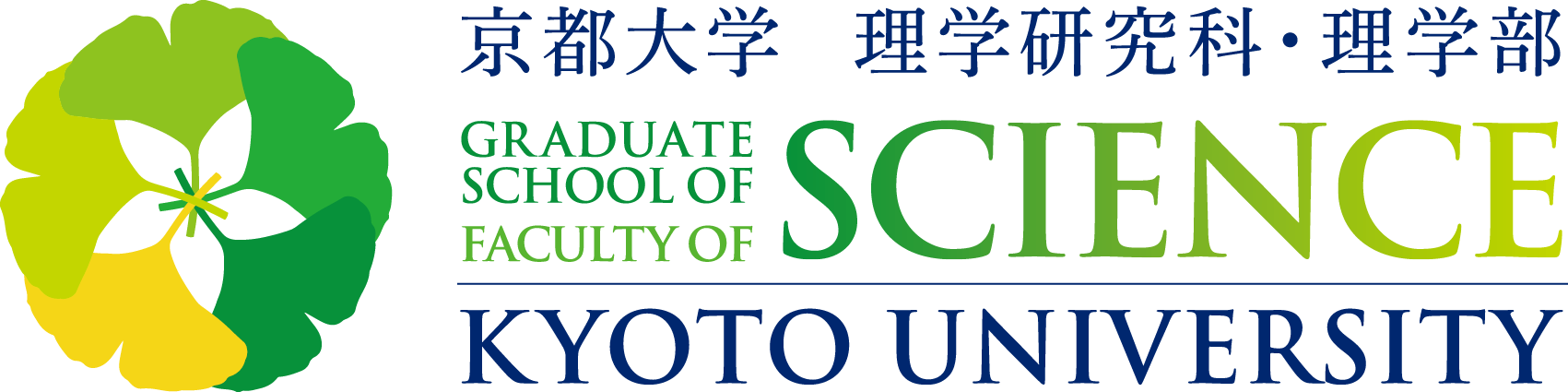本講演会は在職中53歳の若さで他界された玉城嘉十郎先生のご意志に基づいて、没後30年にあたり、ご遺族より奨学のために多額のご寄付をいただき開催されている、公開の学術講演会です。玉城先生は明治19年(1886年)にご生誕、京都帝国大学理学部において理論物理学を講じられ、その門下からは新しい分野を拓く数多くの物理学者が輩出されました。第1回は大学紛争のさなかの昭和44年(1969年)秋、湯川秀樹先生、朝永振一郎先生、寺本英先生を講演者に招いて開催されました。以後回を重ね、さらに2009年度より湯川記念財団からの寄付を得て共催となり、本年度は55年目、63回目の開催となりました。
講演のテーマは必ずしも既存の専門にとらわれず、明日の学問への展望をひらくものを、と心がけて選ばれています。この玉城記念講演会は、理学部・理学研究科及び学内の他研究科の学生、教職員、卒業生や元教員、学外の専門の研究者、さらには一般の方々まで幅広い聴衆を集めています。
第63回玉城嘉十郎教授記念公開学術講演会は、2024年11月14日(木)午後2時より、京都大学北部総合教育研究棟1階益川ホールに、92名の聴衆が集まりました。玉城嘉十郎教授記念公開学術講演会実行委員長の堀毛悟史教授による開会の辞に続き、湯川記念財団の九後太一代表理事から、玉城記念講演会開催の経緯について紹介されました。
第63回となる本講演会の講演は、『物質合成の深化』を共通テーマとして、矢貝 史樹 千葉大学 国際高等研究基幹 教授による「メゾスケール超分子化学」、前田 理 北海道大学 化学反応創成研究拠点長(WPI-ICReDD)による「化学反応の理解と予測」の2つで、約2時間にわたって92名の参加者が聴きました。最後に、田中耕一郎理学研究科長より京都大学 理学研究科の紹介があり、玉城講演会は第1回は異分野交流であり、新しく附属サイエンス連携探索センター(略称:SACRA)学際融合部門に研究展開セクションが設けられたことや、京大理学が独自に産学連携コンソーシアムを設立したことなどが紹介されました。
メゾスケール超分子化学
千葉大学 国際高等研究基幹・教授 矢貝 史樹

身の回りを彩る物質は、様々な原子や分子が集合することで形作られています。分子の集合体と言ってもそのサイズはまちまちであり、タンパク質やDNAがナノメートル($10^{-9}$ m)程度である一方、細胞や液晶などはその単位が数十マイクロメートル($10^{-5}$ m)以上の大きさを持ちます。その中間のサイズを持つ分子の集合体には独自の機能がありますが、そのような物質を合成してゆく化学は、まだ多くの発展を必要としています。
分子の集合体を設計するためには、分子同士の集合の力をコントロールしなければいけません。比較的弱い力による分子の結びつきや組織化により、従来にはないサイズや形の物質をつくってゆく学問が超分子科学です。本講演では、超分子科学を用いて新しい分子集合体を創出し、その形成の過程、得られる形やサイズを様々な解析技術で実証してゆく内容を紹介しました。
例えばある分子を多数集合させてゆくと、あるときは一次元的に集まって、線状になります。DNAが線同士がからみあった二重らせん構造であることはよく知られています。また集合の仕組みを変えることで、線ではなく円、つまりリング状にすることもできます。リング構造も植物や私達の生体の活動に欠かすことのできないものです。光合成を司る分子の集光アンテナ機能や、べん毛の動きに見られる分子モーターなどはいずれも分子が集まって作るリング構造がエネルギー伝達を担っています。このようなリング状の分子集合体を人為的に、精密に作ることができないか、これは大きなチャレンジでした。
バルビツール酸誘導体と呼ばれる色素分子があります。この分子は比較的弱い力である水素結合によって分子集合体をつくりますが、集合時における湾曲の力を分子設計からコントロールすると、ちょうど10ナノメートル直径のリングを作れることが分かりました。原子間力顕微鏡を用いると、鮮やかにそのリング構造を観察できます。この発見をきっかけとし、多種多様な形とサイズを持つ分子集合体を合成する道が拓かれています。リング同士を知恵の輪のようにつなげることで得られるチェーン構造、湾曲しながらも少し歪ませることで得られるらせん構造などがその例です。また光などの刺激を与えることで、それらの形をダイナミックに変化させることもできるようになってきています。
有機化学が比較的小さな分子を精密に合成し、高分子化学がその名のとおり大きな分子を対象とするとしたとき、その間に存在する分子集合体の形を実現してゆく学問が超分子科学になります。特に分子の階層構造とサイズを制御する学問を「メゾヒエラルキー」と名付け、その研究成果と考えを本講演では紹介しました。質疑では、これら分子集合体が示すユニークな特性や機能への期待、また材料としてどのように私達の社会、生活に使われてゆくのかについて展望も含め活発な議論がかわされました。
化学反応の理解と予測
北海道大学 化学反応創成研究拠点(WPI-ICReDD)・拠点長 前田 理

化学反応は、私たちの日常生活や社会全体において、安価な原料から有用な薬剤や機能性材料を生み出す重要な手段として位置づけられています。このような反応の発見や発展は、医療分野からエネルギー産業に至るまで幅広い領域に常に大きな変化をもたらしてきました。そのため、新しい化学反応を開拓し、それを基盤とした革新的な物質や材料を創出することは、人類社会への計り知れない貢献をもたらします。しかし一方で、化学反応は本質的に非常に複雑であり、その開発にはさまざまな課題が伴います。
例えば、常温や常圧の条件下で安定に存在する分子同士の結合を変化させ、新しい構造を形成するには、熱や圧力、光、あるいは触媒といった外部からのエネルギーが必要であるため、それらの反応条件を多岐にわたり、全ての可能性を試してゆくには膨大な手間と時間がかかります。
この課題に対する解決策として、近年注目を集めているのが、コンピュータ技術と量子化学計算を用いた反応の理解と予測です。これらの技術は、化学反応の仕組みを理論的に解明し、新しい反応を効率的に設計することを可能にすると期待されます。もし、反応条件の理解と予測に基づいた効率的な開発が実現すれば、現在直面しているコストや時間の問題を大幅に緩和できると期待されています。
本講演では、量子化学計算を用いた化学反応開発における革新的な試みとして、人工力誘起反応法(Artificial Force Induced Reaction, AFIR法)を中心に取り上げました。この手法は、化学反応における反応物同士に人工的な力を加えることで、ポテンシャルエネルギー曲面上の遷移状態へと効率的に導く技術です。AFIR法の特筆すべき点は、共有結合や水素結合、配位結合、金属間結合、さらにはファンデルワールス相互作用のような多様な結合の組み換えを、シンプルな操作で予測できる点にあります。この方法により、従来の試行錯誤型のアプローチでは捉えきれなかった反応の可能性が明らかにされつつあります。
さらに、AFIR法を用いることで、従来の単一の反応経路に限定されることなく、多数の経路から成る反応経路ネットワークを構築することが可能です。このネットワークには、主生成物を与える経路だけでなく、副生成物を生じる経路や反応物領域での配座異性化経路、さらには中間体領域におけるレスティングステイトを生じる経路など、さまざまな反応パスが含まれています。この多様な経路の中から重要な反応経路を効率的に抽出するため、速度定数行列縮約法という解析技術を開発しました。反応機構の体系的な解明を可能にするだけでなく、反応経路ネットワークの計算効率を向上させる新しい手法です。
本講演では、これらの技術を活用した化学反応の詳細な理解と効率的な開発手法について、具体的な事例を交えながら紹介しました。特に、酵素反応、光反応、不均一触媒、結晶構造探索など、多岐にわたる応用分野においてAFIR法が果たす役割について説明しました。また、近年急速に進化している人工知能(AI)や機械学習技術との融合により、化学反応開発がどのように変革しているのか、その最新の動向についても議論しました。これらの試みを通じて、従来の化学研究における限界を乗り越え、より精密で効率的な反応開発を目指すことが期待されています。最後に未来の化学反応開発に向けた課題や可能性についても議論し、本講演を締め括りました。